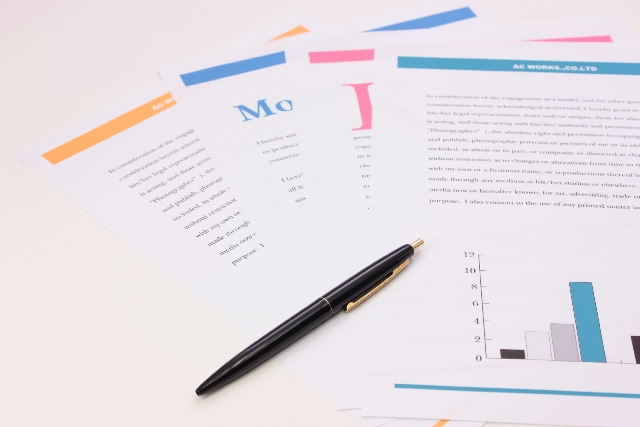


先週末からパートに行き始めたのですが,面接時には10分位しか時間をとってもらえず,又,連絡するとの事で。
その夜に電話で,明日から来てくれという事で,その時に,雇用形態について聞こうと思ったのですが,代理人という事で,伝言を頼まれただけだから,とにかく来てくれとの事でした,それから,約一週間,仕事時間中に帰ってしまう営業者とは,全く話しが出来ないでいます。 夜行ってみたり,電話してみたらしても,つかまりません。
未だに,パートなのか正社員なのか,賃金がいくらか,休日について,保険についてなど,全く分からす働いている状態で,不安すぎます。
辞めたくなってます。無責任でしょうか。
一週間頑張っても全く捕まらないのですが,何かよい方法はありますか?
ハローワークにも電話してみました。
その夜に電話で,明日から来てくれという事で,その時に,雇用形態について聞こうと思ったのですが,代理人という事で,伝言を頼まれただけだから,とにかく来てくれとの事でした,それから,約一週間,仕事時間中に帰ってしまう営業者とは,全く話しが出来ないでいます。 夜行ってみたり,電話してみたらしても,つかまりません。
未だに,パートなのか正社員なのか,賃金がいくらか,休日について,保険についてなど,全く分からす働いている状態で,不安すぎます。
辞めたくなってます。無責任でしょうか。
一週間頑張っても全く捕まらないのですが,何かよい方法はありますか?
ハローワークにも電話してみました。
労働契約をしていないので、働く必要はありません。
ハローワークに電話した結果はどうだったんですか?
※補足について
経営者と話ができて労働契約をするまでは、
まだ働くべきではないと思います。
保険も何もない状態で働いていると、万が一
仕事中や通勤中に事故に遭っても労災の手続きすら
できませんよ。
ハローワークに電話した結果はどうだったんですか?
※補足について
経営者と話ができて労働契約をするまでは、
まだ働くべきではないと思います。
保険も何もない状態で働いていると、万が一
仕事中や通勤中に事故に遭っても労災の手続きすら
できませんよ。
ありがとうございました。
何度も質問に親身に答えてくださって感謝しております。
そして、再度また質問してすいません。
先日労働基準監督署に相談に行ってまいりました。
どうやら・・諭旨解雇というのは変わらなさそうです。
というのは、解雇というのがそもそも曖昧な条件で極端な話、30日前に解雇通知すれば
条件を満たしてるそうです。
ただ、解雇の事由が仕事のミスということであまりにも厳しすぎるということで精神的苦痛をうけたということで、
慰謝料を請求できるかもしれないということです。
それと、諭旨解雇についてですが、上司に諭旨解雇は懲戒解雇の温情板ということでネットで説明されてる
部分が多々あるので、普通解雇にしてほしいと伝えたところ、
ウィキペディアの★以下の文を引用されました。
諭旨解雇;本来は懲戒解雇に処するものであっても、該当労働者が真に認めるなど、情状酌量がある場合に用いられえる。しかし、★普通解雇は「使用者の起因」という要素があり、自ら退職をするより、解雇予告手当、退職金、雇用保険(失業等給付)など手厚い保護を受けることが通常となることから、あまり意味をなさないので、諭旨退職をすることがある。
だから、諭旨解雇というのは問題がないと。
そもそも諭旨というのは、話合いがあったということを示すので、普通解雇にすると後々訴訟の問題もでるし、
わたしが次の就職をする際、下手に解雇とかくと不利になるので諭旨解雇にしたということですが・・・。
ですので、離職票にも諭旨解雇となるそうです。
わたし的には納得できないのですが、法的手段として間違いがないといわれると
どうしようもない気がします。
しかし、世間一般の諭旨解雇に対するイメージは懲戒解雇に近いので、それこそ
次の仕事が決まるのかとても不安です。
履歴書に書く際に、諭旨解雇により退職とか書かなければならないのでしょうか・・。
それと、諭旨解雇されたと履歴書に書かなくてもばれる可能性はあるのでしょうか。
自分のこれから先のことばかり考えて非常に恐縮なのですが、よろしくお願いいたします。
何度も質問に親身に答えてくださって感謝しております。
そして、再度また質問してすいません。
先日労働基準監督署に相談に行ってまいりました。
どうやら・・諭旨解雇というのは変わらなさそうです。
というのは、解雇というのがそもそも曖昧な条件で極端な話、30日前に解雇通知すれば
条件を満たしてるそうです。
ただ、解雇の事由が仕事のミスということであまりにも厳しすぎるということで精神的苦痛をうけたということで、
慰謝料を請求できるかもしれないということです。
それと、諭旨解雇についてですが、上司に諭旨解雇は懲戒解雇の温情板ということでネットで説明されてる
部分が多々あるので、普通解雇にしてほしいと伝えたところ、
ウィキペディアの★以下の文を引用されました。
諭旨解雇;本来は懲戒解雇に処するものであっても、該当労働者が真に認めるなど、情状酌量がある場合に用いられえる。しかし、★普通解雇は「使用者の起因」という要素があり、自ら退職をするより、解雇予告手当、退職金、雇用保険(失業等給付)など手厚い保護を受けることが通常となることから、あまり意味をなさないので、諭旨退職をすることがある。
だから、諭旨解雇というのは問題がないと。
そもそも諭旨というのは、話合いがあったということを示すので、普通解雇にすると後々訴訟の問題もでるし、
わたしが次の就職をする際、下手に解雇とかくと不利になるので諭旨解雇にしたということですが・・・。
ですので、離職票にも諭旨解雇となるそうです。
わたし的には納得できないのですが、法的手段として間違いがないといわれると
どうしようもない気がします。
しかし、世間一般の諭旨解雇に対するイメージは懲戒解雇に近いので、それこそ
次の仕事が決まるのかとても不安です。
履歴書に書く際に、諭旨解雇により退職とか書かなければならないのでしょうか・・。
それと、諭旨解雇されたと履歴書に書かなくてもばれる可能性はあるのでしょうか。
自分のこれから先のことばかり考えて非常に恐縮なのですが、よろしくお願いいたします。
懲戒にすると不当解雇になるから出来ない。だから出来るようにしたの。もうリストラするためになんでもしてきます。
まずユニオンに相談してください。通常はよっぽどのミスがない限り解雇は出来ません。
懲戒解雇になりますが
本当に懲戒になるような会社の基盤を揺るがす大変な事をしたのか?です
懲戒にしてください!と言ったほうが闘いやすい。
まずユニオンに相談してください。通常はよっぽどのミスがない限り解雇は出来ません。
懲戒解雇になりますが
本当に懲戒になるような会社の基盤を揺るがす大変な事をしたのか?です
懲戒にしてください!と言ったほうが闘いやすい。
高度経済成長どは、なぜ「新鋭重化学工業の創出」が要請されたのか、1950年代前半の「経済復興」の実態をふまえて説明しなさい。
と言う問題がでているのですが、どのように解答すればいいでしょうか??
と言う問題がでているのですが、どのように解答すればいいでしょうか??
1955 年以降1965 年頃(昭和30 年代)までに成立した
戦後日本資本主義の「構造」は次のように規定できる。
(1)第Ⅰ部門・生産財生産部門において,巨大
な機械設備・化学装置を装備した新鋭重化学工業が成
立し,これらによって鉄鉱石や石油などの天然資源原
料を除く重要な生産手段の国内自給体制が確立した。
これは,巨大規模の設備投資が膨大な国内の生産のた
めの消費(生産的消費)=需要を産出し,産業連関を
通じて,いっそうの設備投資を引き起こし,国内の拡
大再生産を巻き起こすメカニズムが作り出されたこ
とを意味する。
そして(2)技術革新が第Ⅱ部門(消
費財生産部門)にも波及し,戦前とは異なる,いわゆ
る耐久消費財生産が展開し「消費革命」とよばれる消
費・生活様式の一大変革を引き起こし実現させた。と
りわけ家庭電化製品の分野で変化が起き,1950 年代
前半の時期までは,生産財である重電機が主導的で
あった電気機械部門も,50 年代後半(昭和30 年代)
にはいると家電消費ブームにのり,「三種の神器」と
いわれた白黒テレビ,洗濯機,冷蔵庫,その後「新三
種の神器(3C)カー・クーラー・カラーテレビ」を
中心に民生用製品の量産体制を確立した。
これらの耐
久消費財は急速に家庭に浸透し,それによって家庭電
化製品に囲まれた暮らしが始まったという意味で,生
活様式も一変した。たしかに,戦前,果たすことので
きなかった労働手段中枢の工作機械の国産化も一部
の高級機を除いて,1971 年にはほぼ国産化を完了し,
戦前,軍事・「軍工廠へ『埋没』」していた重化学工業
も民需=民生へと転換した。これは戦前・戦中・敗戦
直後とは異なる「新しい再生産構造」であるといえる。
戦後日本資本主義の「構造」は次のように規定できる。
(1)第Ⅰ部門・生産財生産部門において,巨大
な機械設備・化学装置を装備した新鋭重化学工業が成
立し,これらによって鉄鉱石や石油などの天然資源原
料を除く重要な生産手段の国内自給体制が確立した。
これは,巨大規模の設備投資が膨大な国内の生産のた
めの消費(生産的消費)=需要を産出し,産業連関を
通じて,いっそうの設備投資を引き起こし,国内の拡
大再生産を巻き起こすメカニズムが作り出されたこ
とを意味する。
そして(2)技術革新が第Ⅱ部門(消
費財生産部門)にも波及し,戦前とは異なる,いわゆ
る耐久消費財生産が展開し「消費革命」とよばれる消
費・生活様式の一大変革を引き起こし実現させた。と
りわけ家庭電化製品の分野で変化が起き,1950 年代
前半の時期までは,生産財である重電機が主導的で
あった電気機械部門も,50 年代後半(昭和30 年代)
にはいると家電消費ブームにのり,「三種の神器」と
いわれた白黒テレビ,洗濯機,冷蔵庫,その後「新三
種の神器(3C)カー・クーラー・カラーテレビ」を
中心に民生用製品の量産体制を確立した。
これらの耐
久消費財は急速に家庭に浸透し,それによって家庭電
化製品に囲まれた暮らしが始まったという意味で,生
活様式も一変した。たしかに,戦前,果たすことので
きなかった労働手段中枢の工作機械の国産化も一部
の高級機を除いて,1971 年にはほぼ国産化を完了し,
戦前,軍事・「軍工廠へ『埋没』」していた重化学工業
も民需=民生へと転換した。これは戦前・戦中・敗戦
直後とは異なる「新しい再生産構造」であるといえる。
関連する情報