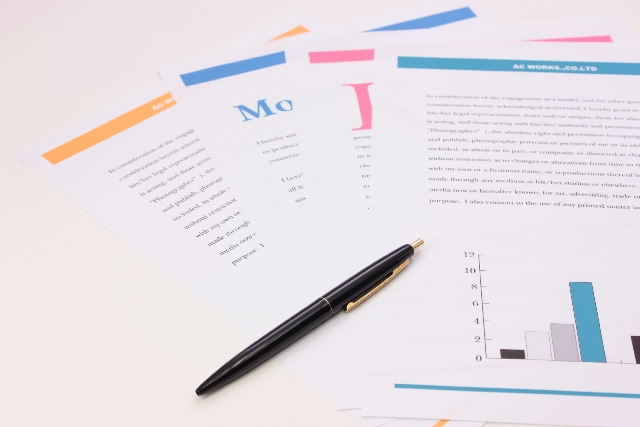


来年3月に、10年間勤めた会社を自己都合で退職します。失業給付を受けたいと思うのですが、具体的な手続きや給付額、給付までの期間等を教えてください。
現在の年収は約300万円です。自己都合で退職すると失業給付がもらえるのは3カ月後と聞いたのでその間にかかる税金や健康保険料等の費用がいくらくらいかかるのかも合わせてお聞きしたいです。
現在の年収は約300万円です。自己都合で退職すると失業給付がもらえるのは3カ月後と聞いたのでその間にかかる税金や健康保険料等の費用がいくらくらいかかるのかも合わせてお聞きしたいです。
失業給付は前の方が書いた通りです。
税金ですが、所得税はかかりませんが、住民税は退職前と同じです。
(去年の年収にたいしてなので、残っている分をそのまま払わないといけません。
給料天引きだと毎月払いですが、退職したら3ヶ月に1回か一括か、まとめて支払いになると思います。)
健康保険ですが、今の健康保険を任意継続した場合は今の保険料の2倍になります。
協会けんぽの場合は資格喪失後、20日以内に自宅住所地を管轄する全国健康保険協会の都道府県支部で手続き
します。大企業の健康保険組合の場合は、そちらに問い合わせしてみて下さい。
国民健康保険は地域によって保険料が違うのでなんともいえません。市役所で問い合わせ
してみてください。参考までですが、私の住んでいる市だと、単身だと年間25万円ほどになるようです。
税金ですが、所得税はかかりませんが、住民税は退職前と同じです。
(去年の年収にたいしてなので、残っている分をそのまま払わないといけません。
給料天引きだと毎月払いですが、退職したら3ヶ月に1回か一括か、まとめて支払いになると思います。)
健康保険ですが、今の健康保険を任意継続した場合は今の保険料の2倍になります。
協会けんぽの場合は資格喪失後、20日以内に自宅住所地を管轄する全国健康保険協会の都道府県支部で手続き
します。大企業の健康保険組合の場合は、そちらに問い合わせしてみて下さい。
国民健康保険は地域によって保険料が違うのでなんともいえません。市役所で問い合わせ
してみてください。参考までですが、私の住んでいる市だと、単身だと年間25万円ほどになるようです。
私は今まで派遣で一般事務員で働いてきましたが、不況のあおりで12月末で派遣契約を切られました。派遣会社からは派遣の事務の仕事は紹介はありますが、長く働きたいので今後は正社員で働きたいと思っています。
ですが、このご時世派遣でも希望の事務職があるのであれば、また派遣で働くべきか、ここは派遣の仕事は断って、正社員で就職活動をするべきか迷っています。
年齢は36歳、独身です。35歳以上の転職活動は、不況でなくても厳しいと聞いておりますので、不安になっています
ですが、このご時世派遣でも希望の事務職があるのであれば、また派遣で働くべきか、ここは派遣の仕事は断って、正社員で就職活動をするべきか迷っています。
年齢は36歳、独身です。35歳以上の転職活動は、不況でなくても厳しいと聞いておりますので、不安になっています
長い間働かれるのであれば正社員で働かれることをオススメします。
ハローワーク、anなどでお探しになってはいかが?
待遇面も月々の収入は減るかもしれませんが、賞与があったり福利厚生の面から全く変わると思いますよ。
大変だと思いますが頑張ってください
ハローワーク、anなどでお探しになってはいかが?
待遇面も月々の収入は減るかもしれませんが、賞与があったり福利厚生の面から全く変わると思いますよ。
大変だと思いますが頑張ってください
退職して、まずしなくてはいけないこととか教えて下さい!
損はしたくないのですが(>人<;)
三月末で、給料が少ない今の仕事を自己退職して、新しい仕事を探す予定です
結婚はしています
が、ダンナだけの給料ではやっていけず、住民税も支払い免除受けるぐらい収入がありません
なので、四月から働ける仕事を探しているのですが、見つからなければ仕事をしない期間があいてしまいます
年金や、保険といったものを支払えない可能性が…
まず、仕事を辞めてしなければならない手続きとかあれば、詳しく教えていただきたいです
損はしたくないのですが(>人<;)
三月末で、給料が少ない今の仕事を自己退職して、新しい仕事を探す予定です
結婚はしています
が、ダンナだけの給料ではやっていけず、住民税も支払い免除受けるぐらい収入がありません
なので、四月から働ける仕事を探しているのですが、見つからなければ仕事をしない期間があいてしまいます
年金や、保険といったものを支払えない可能性が…
まず、仕事を辞めてしなければならない手続きとかあれば、詳しく教えていただきたいです
自分に資格や特技、キャリアが有って、雇用の商品価値がありますか?そうでなくても、現状より収入の高い所へ就職することは難しいと思います。・・・・退職してから無収入の期間がどれだけになるのか未定で不安です。
で、やることは、就職先が決まってから今の勤め先を退職する事です。そのほうが、就職面接においても、積極的な前向きな姿勢であると捉えられます。これが、アドバイスの一番です。
それで、退職時点でしておくことですが、
1、退職前に行う事として、クレディットカードを作って置くこと。 自分に最も有効で、ポイント還元率も高くて、年間手数料の無いものとかを1枚作ります。 無職になると、クレディットカードは作れません。
2、その他、身分保証に繋がる書類は更新しておきましょう。
退職後にすぐすること。
3、離職票を持って、ハローワークに行き、失業保険の支給申請をします。 これを忘れると、失業給付金はもらえません。さらに、登録申請して、新しい仕事の紹介をしてもらえるようにしましょう。
給付期間中に、就職できると、お祝い金として一時金が給付金として別にもらえます。
4、健康保険は今の会社の健康保険に加入しているのでしょうか? 会社を退職すると継続できなくなりますが、任意継続という制度があって、2年間継続できます。 一般的に、会社の健康保険から国民健康保険に切り替えますと、高額な保険料になります。 このため、今の保険を自費で継続したほうが断然安いケースが殆んどです。
5、年金が厚生年金であれば、国民年金に切り替えの申請が必要です。最寄りの年金課に切り替え申請をしてください。
新たに、就職して、厚生年金に加入できれば、自動的に国民年金から切り替わります。
6、ハローワークでは、様々な無料学習コースがありますので、利用されるとよいでしょう。 無料な履歴書も置いてあります。
7、医療機関によっては、無収入であれば、医療費の減額をしてくれる病院があります。
8、健康保険はご主人の会社の保険に扶養家族として届ける方が一番安いでしょう。
9、来年の確定申告で税金が戻ってくる可能性が十分あります。
昨年の所得から計算した税金を考慮して、毎月に給与から源泉徴収されています。多く税金を支払っている可能性があります。次の就職先の給与によりますが、確定申告したほうがよいでしょう。 退職後、ブランクの期間に支払った健康保険や社会保険費も全て所得から控除可能です。申請しないと還付されません。但し、これは24年度分の確定申告となりますので来年の作業です。
年金も国保もそれぞれ、相談窓口で個別相談に乗ってくれますので、減額や免除、延納の相談をされるといいと思います。
以上です。ご参考になりましたら幸いです。
で、やることは、就職先が決まってから今の勤め先を退職する事です。そのほうが、就職面接においても、積極的な前向きな姿勢であると捉えられます。これが、アドバイスの一番です。
それで、退職時点でしておくことですが、
1、退職前に行う事として、クレディットカードを作って置くこと。 自分に最も有効で、ポイント還元率も高くて、年間手数料の無いものとかを1枚作ります。 無職になると、クレディットカードは作れません。
2、その他、身分保証に繋がる書類は更新しておきましょう。
退職後にすぐすること。
3、離職票を持って、ハローワークに行き、失業保険の支給申請をします。 これを忘れると、失業給付金はもらえません。さらに、登録申請して、新しい仕事の紹介をしてもらえるようにしましょう。
給付期間中に、就職できると、お祝い金として一時金が給付金として別にもらえます。
4、健康保険は今の会社の健康保険に加入しているのでしょうか? 会社を退職すると継続できなくなりますが、任意継続という制度があって、2年間継続できます。 一般的に、会社の健康保険から国民健康保険に切り替えますと、高額な保険料になります。 このため、今の保険を自費で継続したほうが断然安いケースが殆んどです。
5、年金が厚生年金であれば、国民年金に切り替えの申請が必要です。最寄りの年金課に切り替え申請をしてください。
新たに、就職して、厚生年金に加入できれば、自動的に国民年金から切り替わります。
6、ハローワークでは、様々な無料学習コースがありますので、利用されるとよいでしょう。 無料な履歴書も置いてあります。
7、医療機関によっては、無収入であれば、医療費の減額をしてくれる病院があります。
8、健康保険はご主人の会社の保険に扶養家族として届ける方が一番安いでしょう。
9、来年の確定申告で税金が戻ってくる可能性が十分あります。
昨年の所得から計算した税金を考慮して、毎月に給与から源泉徴収されています。多く税金を支払っている可能性があります。次の就職先の給与によりますが、確定申告したほうがよいでしょう。 退職後、ブランクの期間に支払った健康保険や社会保険費も全て所得から控除可能です。申請しないと還付されません。但し、これは24年度分の確定申告となりますので来年の作業です。
年金も国保もそれぞれ、相談窓口で個別相談に乗ってくれますので、減額や免除、延納の相談をされるといいと思います。
以上です。ご参考になりましたら幸いです。
関連する情報